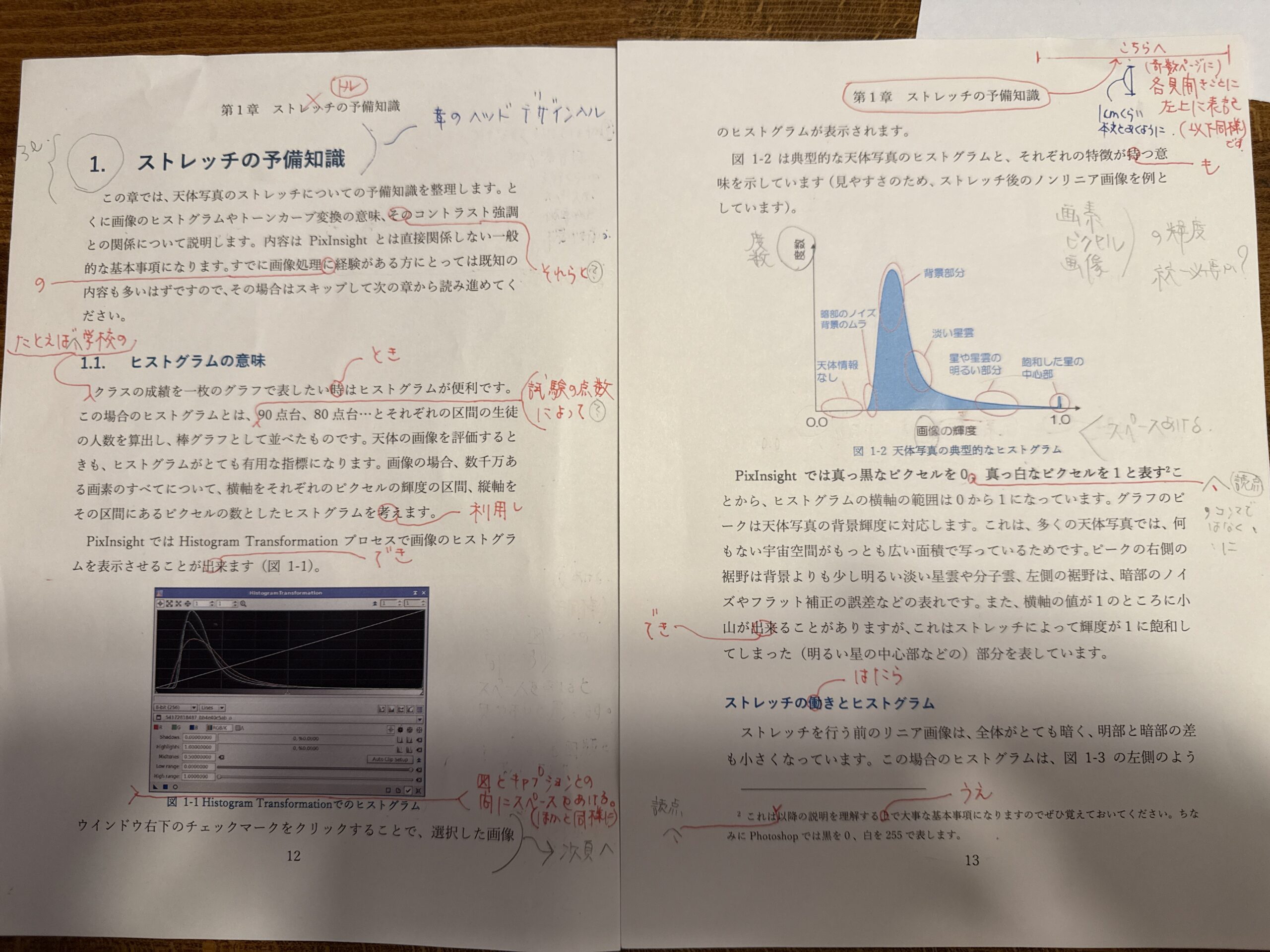「出す、出す」と言い続けて、はや3年。PixInsightの使い方[応用編]の準備がいよいよ最終段階になってきました。著者は我らがだいこもんです。
原稿は7月に完了し8月から校正に入っています。私も一緒に校正に参加しています。1回目の校正が先日終わり、来週あたりから2回目を開始します。それが済んだら、あれしてこれして、またあれして、ようやく出版です。
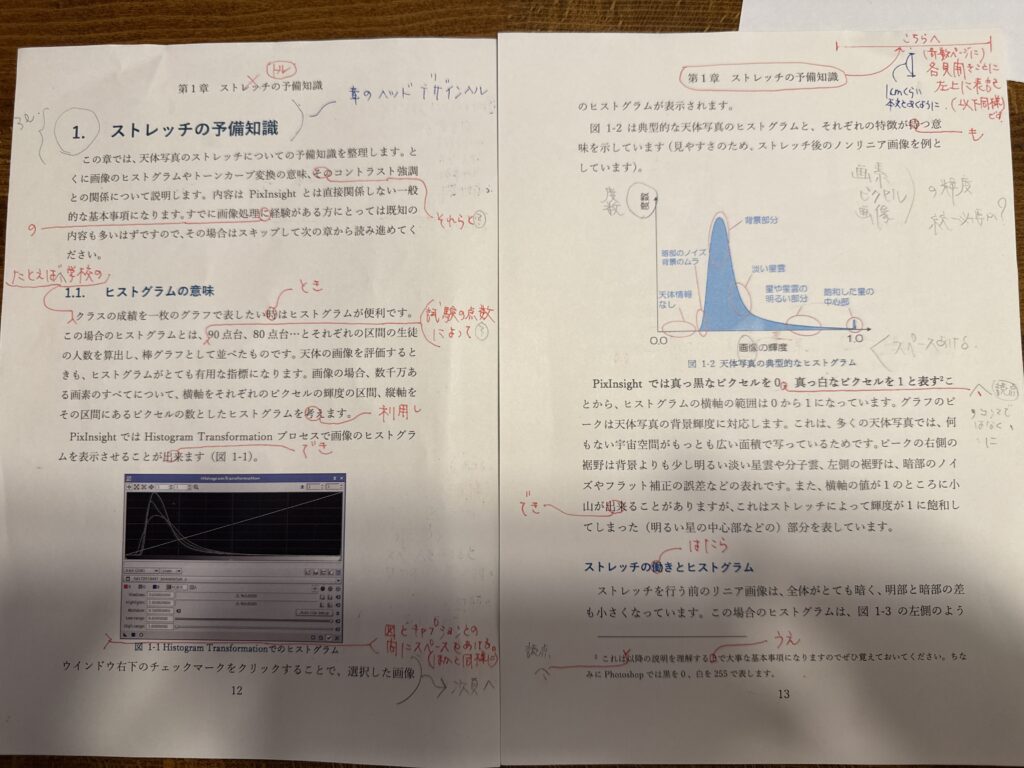
文学好きのだいこもんですので、本書にもちょいちょい文学的な表現が姿を表して面白いです。たとえば「ヒストグラムの傾きが大きい」というところを、だいこもんは「傾きが急峻で」と詩的に表現します。そういうのは、本人は気がついていないですね。きっと。書籍を手にされた方は、そんな楽しみ方もぜひしてみてください!
それでは私が思う本書の見どころです!
引き出しの多さ
基本は誰がやっても同じことが多いです。「PixInsightの使い方 [基本編]」はそのような基礎を理解し、実践できることを重要視しました。しかし応用となると結果にたどり着くのに、いろんな道があります。その道の選び方によって表現が変わってくるのです。だいこもんはこのことをよく「引き出しが多い」と表現しています。
私は気に入ったプロセスは同じ方法で使い続ける派で、まったく使ったことがないパラメータがたくさんあります。一方でだいこもんは新しいプロセスがあると、パラメータを全部試す派です。そんな彼が書いた本書は、私も知らなかったパラメータや使用方法がてんこ盛り。これは多彩な表現につながることが期待できます。
理論の裏付け
天体写真の画像処理は理屈がわからなくても感覚だけでもなんとかいけますし、それはそれで楽しい。昨日、シンセサイザーの使い方のYouTube動画をぼーっとみていました。それで気がついたのですが、ミュージシャンでも感覚でシンセサイザーを使う人と、理論を知って使う人がいるのと同じですね。理論を知った上で画像処理をすると、ミスがあったときの対処や行き詰まったときの打開などに有効です。また自分の求める画像に適した処理を考案できるかもしれません。本書は画像処理の理論的な背景もしっかり説明していますので、興味がある方は読み応えがあると思います。もちろん、難しいと思った理論を飛ばして、PixInsightの操作方法だけ理解することもできますし、それはそれでご自身の画像処理のヒントにつながると思います。
コラムが熱い!
これも基本編と応用編の違いなのですが、基本に関しては「これが正しい」ということはある程度は言えると思います。しかし応用は個性を出す領域でもあるので、その人の趣味嗜好や価値観などにも踏み込むことになり、なかなか「こうあるべき」とは言えない。しかし画像処理をやっている誰しもが思うことですが、本音では自分の価値観を全面にだして「ここは、こうあるべし!」って言いたいのですよね。
本書ではだいこもんは自分の価値観を押し付けないように、めっちゃ自制心を出して執筆しているのがうかがえます。その自制心が内圧となりマグマとなり、自分の考えを出せるコラムで熱く噴火しています。一緒に校正している方とも「コラムが熱いよね」って話しています。応用を読むのが面倒なひとは、コラムを読む目的だけに購入ください!
いやー。たのしみ!!